国試終わった後、そわそわしてる方、ぼーっとしてる方、就職に備えて勉強し始めている方、様々だと思います。
ヤクコジは一回目の国試は落ちました。正直なところ、予備校模試の成績は悪く国試は落ちるだろうなと思って受けた感じでした。
それでも思ったより点数が取れて合格最低点まであと数点というところでした。
もちろん悔しかったです。どうせなら国試一回目で受かりたかったですし、ただ落ちたものはしょうがないという腹をくくるまでにはそう時間はかからなかったです。
追記 10/4 学生の方向けの就活支援サービスについての記事も書きました!
実習や国試対策で忙しい薬学生へ!失敗しない就活のために今すぐすべきこと
✔ 国試に落ちてから、予備校が始まるまでの期間の過ごし方
✔ 予備校(薬ゼミ)の年間カリキュラムと、各期間の効果的な勉強法
✔ テストを最大限に活用し、効率的に点数を伸ばすためのコツ
✔ 浪人生活を乗り切るための、モチベーション維持のポイント
✔ 予備校の講師を効果的に活用するための注意点
~予備校が始まるまでの期間~

予備校に通う前までの期間はバイトしたり好きな食べ物である海鮮丼を食べに行きまくったりしていました。
年度によって若干予備校の開始時期が異なったりします。
ヤクコジの時は5月のGW明けくらいから予備校が始まりました。
(予備校サイトを確認したところ、4月21日から開始のようで、以前より開始が早くなってますね…)
また、自分は薬ゼミの一年通学コースに通っていました。
国試が終わってから予備校が始まるまでの間は、リフレッシュ期間だと考えていたのでほとんど勉強しませんでした。
最後の二週間くらいだけちょっと勉強するくらい。
もう人生において最後の長期休暇だとなんとなく考えていましたね。
薬ゼミ一年通学コースは簡単にまとめるとこんな感じでした。
(何度も書きますが、年度によって講座開始時期などは若干異なります)
- 5~9月まで青本講座
- 9~11月まで青問講座
- 12月頃~2月の本番まで総復習講座とやまかけ講座で仕上げ

【 東大医学部 睡眠専門医 推奨 】 アイマスク 無重力フィット 完全遮光性能 99.99% [国際規格 ISO、FDA認証 取得済] 睡眠・旅行用 携帯用ケース付
~青本講座期間(インプットメイン)~
個人的にここが勝負の期間

入校してからのガイダンスでおそらく言われると思います、青本講座の期間がとても重要だと。
じっくりと青本で国試対策をする機会っておそらく初めてだと思います。
それくらいじっくりと解説してもらえます。
ただ、9月以降は膨大な量の問題をこなしていくので、一々詳しく振り返るという時間が取れません。
なのでこのインプット期間に死に物狂いで自分でささっと振り返ることができる青本を作っておく必要があります。
死に物狂いといっても、講師の方たちが自身の青本を映しながらメモや図解を書きやすいように示してくれます。これが非常にわかりやすい。
講師は皆国試対策のプロなので、国試の過去データに基づいた点取りポイントを示したり、
中にはその内容に即した論文の内容を示しながら解説してくださる講師もいました。
薬ゼミで講義を受けるまでは、どうせ国試の解き方とゴロくらいしか教わらないんだろうと思っていましたが、
良い方にどんどん裏切っていってくれて講義を聞くのが楽しかったのを覚えています。
勿論講義を聴くだけじゃありません。一日ごとの内容を翌日に復習する日々の振り返りテスト、
一週間ごとの週間復習テスト、月間ごとの内容の月間テストがあります。
これらを受けていくだけでも最初のうちはしんどいですが、そのうちこの流れに慣れていきます。
テストは点数が大事じゃない! 点をupさせる為の最高の材料!!!
よくいるのが、学内テストや模試を受けた直後の点数を気にしすぎて復習が手につかない人
ものすごくもったいないです。
特に学内の週間テストや月間テストは、多すぎなく短すぎない範囲で適度に自分がどれくらいできているのか。
また自分の立ち位置は予備校内でどれくらいなのか客観視できるので、とても良い勉強材料です。
下手に必須の問題集とか買って中途半端にやるよりは、こういった資材を何度も復習して周回できるようにしておいたほうがいいと個人的にい思いますね。
モチベーション維持のため 勉強友達は居たほうがいい
自分はあえて知り合いがいない少し遠めの校舎に通っていました。
流石に一人でやっていくのはメンタル的につらいかもなと思い一人知り合いを作りました。
結果的にこの方に物凄くお世話になり助かりましたね。
浪人生活中、コロナにかかり1か月弱くらい通学ができずに家で勉強をしていました。
その時にとてもお世話になりました。なので、皆さんも浪人中は孤独に頑張る!ということに固執している方がいたら、
ぜひ一人は知り合いを作ってたまに愚痴をこぼしあったり助け合ったりしてみてほしいです。
~青問講座期間(アウトプットメイン)~ ひたすら問題解きまくる
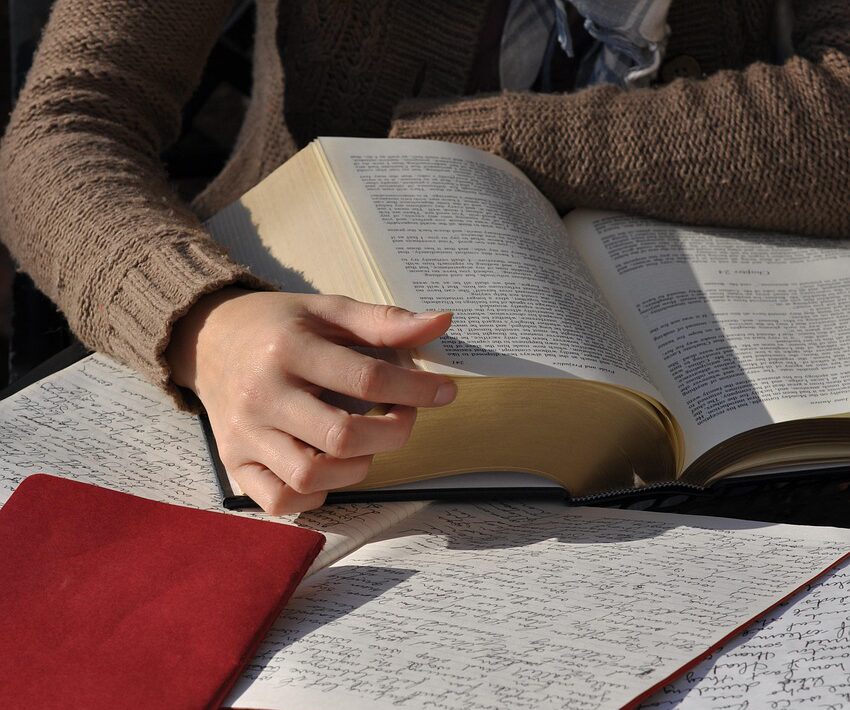
9月に入ってくるまでにもうインプットしまくったので、ひたすら青問やそれまでにこなしてきたテストを復習していく期間になります。
青本期間をしっかりこなしてきた人であれば、ここからは少し退屈になるかもしれません。
青問は毎年大幅な問題の変更があるというわけではないので、自力で解ける問題も少なくないと思います。
講義としては、講義ごとにピックアップした問題を時間内で解いて、解説聞いてまた解いて解説聞いてという流れなので、割と単調です。
そして自習や帰宅後に周辺問題を解いてわからない事は青本のメモなどで復習する。
それでもわからなければ講師に質問をするといった感じでした。
ちなみに、ヤクコジは9月まで講義で必要な問題以外はほぼ青問を解いていませんでした。
白問という知識の定着に最低限必要な問題のみをそろえた物を薬ゼミ生は渡されていたので、青本期間の問題演習はそれをメインしていました。
※自分の時と白問の内容がかなり変わったみたいなのでしっかりと講師に活用方法確認するように!!!

意外と盲点
12月くらいまでに疑問点は講師に聞きまくれ!
これ後からわかるのですが、12月くらいになってくると予備校の講師が全国各地の大学に出張講義などしに行きまくるので、
聞きたいときに居ない!!! という事態が普通に起こりえます。
なので、後で聞けばいいやとかは絶対しないようにしましょう。
あと12月くらいからはめっちゃ質問並びますので日によっては1時間待ちとかにもなったり…
十分気を付けてください。(一人が講師を数十分占領したりします)

【Amazon.co.jp限定】明治プロビオヨーグルトR-1 ドリンクタイプ 112g×12本 強さひきだす乳酸菌【クール便】
まとめ
- 5月からのスタートダッシュが大事
- 週間テストや月間テストの復習は得点upのチャンス
- 勉強友達は一人は作ったほうがいい
- 12月までに疑問点は質問しまくる
万人に当てはまるというわけではないと思いますが、
実際に国試浪人を経て思ったこと感じたこと
挫折してしまった人になかった要素などをまとめてみました。
今回は以上となります。ありがとうございました。

